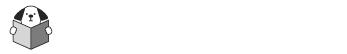みなさん、このキャラクターを一度は見たことがあるのではないでしょうか?↓↓

今回はドン・キホーテ(現パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)を一代で築き上げた安田隆夫氏についてご紹介します。
経営に対する考え方や彼が挑戦してきた経営方法について、彼の執筆した経営に関する自伝本をもとに探っていきたいと思います。
また、現在も成長を続けるドン・キホーテの強みや口コミも調査していきましょう。
目次
- 安田隆夫氏の小売業界における経営戦略とは
- 安田隆夫氏の経歴
- ドン・キホーテの口コミ・評判から見る強み
- 安田氏独自の経営戦略
- 安田氏の最新情報
- 既刊紹介
- インタビュー記事
- 常識と戦い続け、流通革命に挑む / ドン・キホーテ
- ドンキホーテHD、米国で「持ち帰り総菜」店舗展開へ
- 中小企業から大企業へと生まれ変わるための絶対条件。部下への権限移譲が社長の自己表現への王道だ!
- 【ドンキ安田】これから日本は、さらに「ディスカウント化」する
- セレブの心理をくすぐります!ドンキホーテが東京・白金に実験店開業
- ドン・キホーテ創業経営者 安田隆夫「私が早期引退した理由」
- 『ドン・キホーテ創業者』安田隆夫の「現場主義と顧客最優先主義に徹して」
- 日本の農畜水産物は「第二の自動車産業」になる――安田隆夫(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス創業会長兼最高顧問)
- 33期連続増収増益。ドンキの強さをつくった権限委譲カルチャー
- その他
- 検証まとめ
安田隆夫氏の小売業界における経営戦略とは

さて、まずは安田氏が記した著書の内容を見てみましょう。
著書「流通革命への破天荒な挑戦!」の中では彼がどのような取り組みをしているのかについて記述されています。
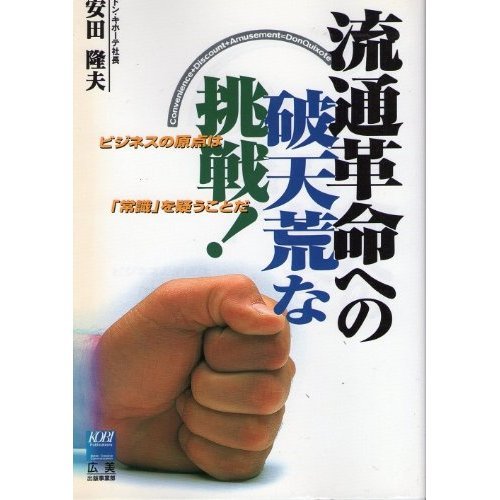
まず一番目を引くのはドン・キホーテ社の経営のコンセプトだと思います。
ディスカウントストアなどの小売業においては、通常のマーケティングではマーケティングミックス(4P/5P)と言われる指標がよく用いられますよね。
- 製品(Product)
- 価格(Price)
- 流通(Place)
- プロモーション(Promotion)
- 人々(People)
- 包装(Package)
もちろん同社もこのマーケティングミックスについては抑えているとは思いますが、安田氏は別のコンセプトを持っておりました。
それが、「CV+D+A」だそうです。
- CV=コンビニエンス(利便さ)
- D=ディスカウント(値下げ、安さ)
- A=アミューズメント(楽しみ)
ドン・キホーテ社では、「必要だから行く」ではなく「面白いから行く」を大切にした結果同業他社との差別化ができたそうです。
安田氏はアミューズメント性の大切さについて、便利で安いだけでは人は集まらないと記載しております。読者の方の中にも「ドンキに遊びに行く」「楽しい場所だ」というイメージのある方も多いのではないでしょうか?
所狭しと並べられた商品に、目を引くPOPなどが飾られてあり必要なものだけを買いに行く場所には留まっていませんよね。
また、小売業について下記のようにも語っています。



小売業をこのように捉えている人は少ないのではないでしょうか。
とはいえ、ドン・キホーテの商品の価格の安さは確かに大きな魅力のひとつです。
価格を安く抑える為にドン・キホーテはある仕入れの掟を徹底して実行に移しているそうです。
その他にも「5つのセオリー」があります。
- クイックレスポンス(仕入先からの売り込みに対し素早く回答すること)
- すぐに現金を払う(即金で仕入れをすべて行う)
- 相手にリスクを負わせない(返品をせず、買い取る)
- ある程度まとまった量を仕入れる(需要と供給のバランスを見て”ある程度)
- 売り込み着手容易性(仕入先への手続きを簡易化させる)
いわれてみれば当たり前のようなことかもしれませんが、これを実現するためには臨機応変さが要求されます。
そのため、この方法を実行している企業はほとんどなく、これを実行できていることがドン・キホーテの強みのひとつなのです。
安田隆夫氏の経歴
ここで、次々と新しいことに挑んでいった、安田隆夫氏のプロフィールと経歴についても見ていきましょう。

プロフィール
| 生年月日 | 1949年(2020年時点で満71歳) |
|---|---|
| 出身 | 岐阜県大垣市 |
| 出身高校 | 岐阜県立大垣南高等学校 |
| 出身大学 | 慶應義塾大学法学部 |
経歴
| 1978年 | 東京都新宿区に泥棒市場を開店 |
|---|---|
| 1980年 | 株式会社ジャスト(現株式会社ドン・キホーテ)を設立 |
| 1989年 | 第一号店である「ドン・キホーテ」府中店を開店 |
| 2015年6月 | 会長兼CEOを退任 |
| 2019年1月 | PPIHの再び取締役(非常勤)に就任 |
安田隆夫氏は1949年に岐阜県大垣市にて生まれました。2015年に行われたインタビューでは学生時代は「ガキ大将」の一面も有ったが、一方で「休み時間には読書をしている」といった一面も明らかになっています。
「10代の頃、自分は社会に適合していないという劣等感があった。一方で他の人たちとは違う自信への誇りがあった。」と安田氏は言います。きっとこの他の人たちとは違う自信への誇りが、安田氏をここまで偉大な人物にさせたのでしょう。
そのような考えや気持ちから、安田氏は「俺は波瀾万丈の生き方をしたい」という強い思いを持って慶應義塾大学に進学をしました。しかし、田舎育ちであった安田氏は都会っ子が多い環境に当時は馴染めず、ドロップアウトしてしまったそうです。。
そんな安田氏が就職したのはとある中堅不動産会社。就職の理由も「早期に独立するチャンスを掴もうとしたから」と語っております。しかし就職した不動産会社はオイルショックの煽りで直ぐに倒産してしまいます。
港湾労働や新聞の拡張団で日銭を稼いで暮らしながら、やがて安田氏は処分品やサンプル品を安価で販売するビジネスにたどり着き、1978年、29歳で西荻窪に「泥棒市場」をオープンさせたのです。
ドン・キホーテの起点になったエピソード
安田氏がドン・キホーテの前身である「泥棒市場」でナイトマーケットの可能性に気が付き、やがてドンキホーテを創業するに至っています。ナイトマーケットの可能性に気付き、差別化に成功したエピソードを紹介いたします。
「泥棒市場」閉店後に安田氏が片付けをしている時、お客さんが来店しました。店内は狭く、商品を路上に積み上げ、照明つけたまま片付けをしていたことから、営業中と勘違いしたとのことです。
安田氏は喜んでお客さんに商品を売ったそうです。ちょうどコンビニが11時までしか営業していなかった時代に、コンビニより長く店を開けることで差別化を図ったのです。
今では当たり前になってしまった深夜営業も、当時は革新的な動きでした。営業中だと思い、間違えて店舗に入ってしまったお客さんにも、今のドン・キホーテの第一歩となるきっかけをくれたと思うと感謝したいですね。
今もドン・キホーテの深夜営業によって利用者たちは深夜でも欲しいものが手に入るという便利な生活を手に入れたきっかけのようなエピソードです。積極的に周りがやっていないことに恐れずチャレンジしたことが成功につながっていったのでしょう。
また、2015年には一度退任していますが、退任後もチャレンジ精神は尽きること無く、2019年2月、安田隆夫氏は取締役に復帰しました。
実は2015年の経営引退後も、ドンキの海外展開を指揮していたという安田氏。また、ユニーの買収交渉でも中心的な役割を担ったのは安田氏だった、とのことです。
株式会社ドンキホーテホールディングスは2019年2月から商号を変更し「パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(略称PPIH)」となり、株式会社ドン・キホーテは連結子会社となりました。
下記が現在のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの情報です。
| 企業名 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 本社所在地 | 東京都目黒区青葉台2-19-10 |
| 設立 | 2019年2月1日に商号変更(株式会社ドン・キホーテは連結子会社に) |
| 資本金 | 231億5千3百万円(2021年6月30日現在) |
| 売上高 | 1兆8,312億80百万円(2022年6月期) |
| 代表者 | 吉田 直樹 |

つまり安田氏は株式会社ドンキホーテの取締役ではなく株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの取締役(非常勤)ということになります。
PPIHは国内・海外のディスカウント事業のみならず、不動産開発会社やITの会社、アピタ・ピアゴなどのユニー株式会社など様々な子会社を有しておりますので、安田氏はドン・キホーテのみならず、全ての事業に携わっていると考えられますね。
安田奨学財団の取り組み
安田氏の経歴に慶應義塾大学への進学と挫折について記載しましたが、そういった自身の経験が影響してか、ドン・キホーテ創業25周年という節目に「安田奨学財団」を設立しております。
この財団は経済的困難を抱える留学生を対象に奨学金支給を基本とし、他国との交流などを目標に活動を行っているそうです。
国内の留学生の数は「留学生受け入れ10万人計画」を皮切りに増加傾向にあり、2004年には11万人を超え、その結果人材育成やネットワーク形成が急務とされてきました。
これらの背景には、経済的・政治的観点が潜んでいると思われがちですが、安田氏は「文化的・人的交流を深める」という独自の目的を掲げ財団設立に踏み切ったことを公式サイトで語っております。
恐らく、自身の学生時代の苦労から留学生たちが抱える経済的困難に共感を覚え、「支援をすることで優秀な人材を育成し未来に貢献したい」と願ったのでしょう。
安田氏の人柄に迫る!意外な一面で親近感が湧く?!
公式サイトやインタビュー記事を読めば、安田氏の経営者としての姿勢や今後目指すべき方向性が自ずと見えてくるでしょう。
…しかし、これらの情報はある程度ビジネスの知識がある人間にとっては受け入れやすいものの、一般人にとってはハードルが高い。
せっかくドン・キホーテや安田氏に興味を持ったとしても、知識がないからといって諦めてしまうのは非常にもったいないので、ここでは安田氏の人柄など「親しみやすい一面」をご紹介します!
①格闘技好き
安田氏は格闘技に対し熱心な一面があり、スポンサーを引き受けた経験もあるそうです。
http://gbring.com/sokuho/news/2007_10/1015_wvr_04.htm
こちらは2007年10月に行われた「日本総合格闘技協会」「株式会社ワールドビクトリーロード」の設立発表会見の様子を記したものですが、記事には安田氏が副会長に就任した旨が記載されています。
以下一部抜粋しました。
私も格闘技の熱狂的なファンで、ファンの心理は手に取るように分かるつもりです。これだけ人気があって、潜在的なファンがいる。しかも試合に出たい選手が山のようにいて、それが実現しない事態が、先ほども申し上げたように不条理だと思います。(一部省略)
無名の選手を育成するため、実業団や一般的なスポンサー企業に代わりバックボーンとしての役割を担いたいと安田氏はつづけています。
若い才能をつぶさず、彼らが活躍できる現場を率先してつくっていく―――下の世代へと受け継いでいこうという姿勢が、ここからも垣間見えますね!
②「レッツゴードンキ」の名付け親?!
レッツゴードンキは競走馬の名前で、恐らく競馬好きのあいだで最も有名なのは2015年菊花賞でしょう。情報によると、レッツゴードンキには元々「行きたがる癖(多分調教師の指示を聞く前に動き出してしまうことを指しているのでは…)」があったもののそれを調教し臨んだ菊花賞で勝利をつかんだそうです。その後レッツゴードンキは2019年に引退しています。
…さて、では一体なぜ、ここで競馬の話しをはじめたかといいますと、じつはレッツゴードンキの名付け親は何を隠そう安田氏本人だからです!以下、菊花賞を制した当時のレッツゴードンキの廣崎オーナーによるコメントです。
「ファンと一緒に見ようと、直線のフェンス沿いで見ていました。(馬名は)親しくしてもらっている(ディスカウントストア)ドン・キホーテ創業者の安田隆夫さんにつけてもらいました。今回の勝利はすべて関係者のおかげ。感無量です」
引用元:http://race.sanspo.com/keiba/news/20150413/pog15041305060008-n1.html
以上のエピソードから、安田氏の交友関係の広さが窺えますね!と同時に、安田氏の革新的な経営方針や挑戦しつづける姿勢の裏には、パワフルなコミュニケーション能力と強い好奇心が大きく働きかけていたという事実が見えてきました。
③部下とのコミュニケーションは「悩み相談への対応」で決まる?!
「他人の悩み相談、聞き流す派?腹を割って話す派?」
安田氏関連のインタビュー記事から、このようなタイトルを発見しました。…確かに、社員にとって報連相は非常に重要なポイントであり、これらが正確に行えるかどうかで色々と左右されてしまうものですが、それもこれも上司の応対ひとつでガラッと変わってしまうものですよね…。
このあたりについて、安田氏はどう考えているのでしょう?
商売の最前線である売り場は、自分の成長の場である半面、仕事上の悩みや不安を抱えることも少なくない。グチが出ることもあるだろう。そうした場合、上司はどうすべきか。私が指導してきたのは、真摯な態度での即対応だ。聞き流さず、きっちりと受け答えすべきだ。
引用元:https://president.jp/articles/-/20787
ドン・キホーテの最大の強みは新陳代謝…それは商品のディスプレイはもちろん、現場や社員の考え方も時代の流れと消費者ニーズに合わせてアップデートしていくことを意味しています。ただ、ニーズに見合った成果が求められるのは社員にとって大きなプレッシャーになってしまう…。
こういう時、代表自ら社員に寄り添ってくれるのは非常に心強い!企業の利益追求を優先するなら正直社員ひとりにかまっている余裕はなくて当然なのに、それでも気を配る安田氏の様子を想像すると、社員にとってもそして消費者にとっても「つねに周囲の声に耳を傾けてくれる場所=ドン・キホーテ」なのだと、改めて実感したのでした。
④安田氏流新人教育の極意は放任主義?!
消費者や社員の声に耳を傾け、周囲のニーズに特化した「答え」をつねに提供しつづけることを信条とする安田氏の経営理念は、恐らく今後の時代の変化にも柔軟に対応していける要となるでしょう。
時代の移り変わりによって、消費者のニーズはもちろん、新人の働き方や求める職場環境も変化するからこそ、より重要になっていくのが「教育」だと思います。コロナとの兼ね合いや男女平等と向き合わねばならないなか、安田氏は教育についてどのように考えているのでしょう?
(中略)それも各部門の担当者全員に、それぞれ専用の預金通帳を持たせて商売させるという徹底した権限委譲を行った。つまり、各部門の担当者が「個人商店主」になるというシステムだ。この「権限委譲による個人商店主システム」は、後年のドンキ最大のサクセス要因になった。
引用元:https://president.jp/articles/-/16412
初期のドン・キホーテの経営状態が安定するまで様々な策を講じた安田氏は、最終的に「担当者に店を任せる」という決断を下した結果、現場でイキイキと働く社員の姿を頻繁に見かけるようになったそうです。
各企業のルールや方針にYESマンであることこそ社会人の真髄といわれる現代において、商品知識が乏しい社員に任せるという思い切った決断ができるのも、安田氏が彼らの成長と才能を信じているからこそ良い意味で「放任主義」が貫けるのかもしれません。
⑤後輩から「麻雀強し」のお墨付き!
先日、Yahoo!記事に以下の内容が掲載されていました。
麻雀も仕事も「運が7割、実力3割」。「文藝春秋」2022年5月号より、サイバーエージェント社長の藤田晋氏による「わがギャンブル経営哲学」を全文転載します。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1a9278e18d34c4f3dba20a4306c5f207c6ef3d42
サイバーエージェントといえば大ヒット中の「ウマ娘」の生みの親。Yahoo!記事のインタビューのように、藤田社長の手腕やウマ娘ヒットの秘訣を知りたい!という目的で様々な媒体から注目されていること間違いなしでしょう。
…さて、ここでお話したいのはあくまでも藤田社長についてではなく、以下一文に注目していただきたい。
今まで卓を囲んだ経営者のなかで一番麻雀が強いと思ったのが、ドン・キホーテの安田隆夫さん(現・創業会長兼最高顧問)。技術面もさることながら、とにかく最後まで一生懸命に集中力を切らすことなく打ってくる。最終的には勇気や度胸、情熱がないと勝てない。
複雑且つ時間がかかるゲーム「麻雀」…インタビュー記事にも掲載されているように、終始ゲーム感覚で対戦するなら感情的になって負けるのもある意味いい思い出ですが、最後まで勝ちを諦めず粘り強くタイミングを図るなら、アドバイスは「キレたら負け」のみだそうです…。
安田氏の麻雀の強さは、勝負師としての才能はもちろん、途中で投げ出さず一点集中状態を持続できる、それは彼の性格的な忍耐強さはもちろんのこと、長年経営者として時代と向き合ってきた経緯も大いに関係しているのでしょう。
⑥周囲との違いをユーモアに転換
何かしらの成功者にとって「過去の苦労話」は付き物で、それは安田氏も例外ではありません。ここで重要なのは、「劣等感など“ネガティブな経験”をいかにポジティブに昇華できるか」ではないでしょうか?
努力が報われず自信喪失しそうになった経験を経て、どうやって夢を叶えていったか…現状に至るまでの経緯に成功者個人の個性や魅力が宿るのであり、きっと一般人はその物語に惹かれるのだと思います。
そういう意味で言うと、安田氏は「周囲との違いを認め、“ユーモア”に転換」できた経営者なのでは?例えば以下インタビュー記事では次のようにコメントしています。
人の心を掴むのはどうすればいいか。心のひだに触れて、分け入っていくこと。これを商売の“座標軸”にしないと、受け入れられない。
引用元:https://www.news-postseven.com/archives/20150517_320450.html/2
人と違う人生を望みつつ、しかしその「違い」が上手く言語化できずにモヤモヤを抱えていた若き日の安田氏は、それがそのまま「顧客にとって魅力的な商品の販売方法」に繋がるということに気付いたそうです。
この転換が後にドン・キホーテというユーモアたっぷりのショップ誕生のキッカケになるとは…誰が予想できたでしょう!
⑦「顧客のニーズ=欲求」と真摯に向き合う姿勢
顧客の購買意欲は、その時の流行や時制に大きく左右されはしますが、ザックリ言ってしまえば「個人の欲求」によるものが大きい。「もっと流行に適した洋服やメイクを身につけたい」「もっと自分の生活を便利で豊かにしたい」というように、物や情報が簡単に手に入れられる時代になっても、むしろこういう時代になったからこそ、人はますます自分の欲求に素直にならざるをえないのでしょう。
…しかし、いくら欲求は尽きぬと言っても、出費できる額にはどうしても限界がある。
そのため、「もっと○○が欲しい」の枕詞に「リーズナブル」という単語をつける必要性が生じてしまいます。
「リーズナブルに、利便性抜群でセンスの良いモノを手に入れたい」
このような顧客の欲求に全力で応えられるのは、経営者として、そして人間として自身の欲求に素直な安田氏特有の才能である、という旨が記載された記事を発見しました。以下一部引用文です。
顧客の心に刺さる商品を仕入れて販売するノウハウはドンキの強みの1つだが、その根底にあるのは、顧客の潜在的な欲望を見抜く“目”だったのではないだろうか。
引用元:https://www.zakzak.co.jp/eco/news/180919/eco1809190009-n2.htm
日本では未だに「誰もが当たり前に持っている欲求」を剥き出しにする行為に対し抵抗がありますが、安田氏自身が金銭や物欲、そして他人からの承認欲求を素直に受け止められる人間性だからこそ、人の購買意欲をくすぐる商品陳列や独自の経営方針が打ち出せるのかもしれませんね。
⑧安田氏の「オールハッピー」精神から学んだ経営者が他分野で活躍
人間の本質というものは「他人」を介してでしか見えてこないもの。いくら本人が周囲に細やかな気遣いが出来るだけではなく、人一倍努力を惜しまない性格だったとしても、他人の口で語られることで、はじめて周囲から「この人はこういう人間性だ」と認識されるのでしょう。
経営者もまた然り。彼らが育てた後輩たちが社会に出て活躍していくなかで、過去に学んだ経験を活かし語ることではじめて、「先人たちの手腕」が広く認識されるのではないでしょうか。
男性不妊の課題解決に取り組む「ミツボシプロダクトプランニング」代表者の向井氏は、かつてドン・キホーテグループの子会社で社長を務めていたそうです。不妊治療経験者の立場からパートナー双方で課題解決に取り組めるようなプロダクトづくりに挑む向井氏が過去にドン・キホーテで学んだのは、商売の仕方と「オールハッピーの姿勢」だと、以下インタビュー記事にて語っています。
安田会長から学んだことで最も印象的なのは、“オールハッピー”の姿勢です。自分と顧客と世間の“三方よし”を目指すという意味ですが、お互いが長期的に良好な関係を築くことの大切さを知りました。
引用元:https://net.keizaikai.co.jp/66305#i-1
「店舗と消費者」「経営者とクライアント」「先輩と部下」…様々な関係性がWin-Winを築き、「長期的」な付き合いが出来るようになる、それこそビジネスの極意なのかもしれません。
⑨安田氏の「日本経済への反逆精神」から学べること
現場主義や顧客優先主義、土地や消費傾向に適した店舗づくりなど、独自の方法論で大きく成長を遂げてきたドン・キホーテ…その立役者といえば、安田氏を置いて他はいないでしょう。
安田氏のインタビュー記事からは、波乱万丈な人生がドン・キホーテ成功の要因へと直結している事実が読み取れますが、その奥に、氏がずっと抱えてきた「反骨精神」が燻っていることが、以下記事により明確に浮かび上がってきました。
「日本一地価の高い所に店を構えて夕方6時には閉めてしまう。こんなやり方は絶対永続きしない」
引用元:https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/276212
この記事では、昨今軒並み経営難に追いやられている老舗百貨店を例に、「午前中に開店し贅沢品を販売して夜には閉店する」昔ながらの手法と、「日用品の隣にまるで当たり前のようにブランド品を並べ夜中も経営する」ドン・キホーテの独自路線とを比較しています。
安田氏によると、このような独自路線にたどり着いた理由のひとつが「目立つため」だそうです。泥棒市場を立ち上げた当時、大型チェーン店全盛期だった時代とぶつかってしまったこともあって、どうしても異なる路線を突き進むしかなかったという。
通行人が思わず立ち止まりたくなるようなディスプレイをしつつ、ひたすら実直に経営をつづけてきた…その背景には、あの時代を生きた者にしか抱けない「日本経済への反逆精神」が潜んでいるのでしょう。
⑩人の痛みに寄り添うビジネス論
産経新聞WEB版にて連載されている「”100円の男”矢野博丈の哲学」では、様々な経営者の人生観とビジネス論が紹介されていますが、そのなかで「安い店より優しい店 ”人を動かすのは人の心だ”」というタイトルの元描かれているのは、筆者の知人でもある安田氏についてです。
(中略)街でホームレスを見て私が「ひとごとには思えん。わしも紙一重じゃったけえ」とつぶやいたら、安田さんも「ホームレスが公園で飲んでいると輪の中に入りたくなる」という。
引用元:https://www.sankei.com/article/20231017-T45ISS3DG5MBTPJPBNPUDGSLJU/
安田氏のビジネス論は彼の波乱万丈な人生があってこそ、というのは最早言わずもがなですが、その根底に「弱い立場の人間に寄り添う姿勢」が潜んでいるというのは、親しい仲でないとなかなか気付けないでしょう。
(中略)安田さんも就職した会社が倒産するなど波瀾(はらん)万丈な人生を送っていた。それだけに、人の心の痛みが分かるのだろう。店にも温かさがにじみ出る。結局、人を動かすのは人の心だ、ということだろう。
だからこそ、安田氏のビジネス論や後進の育て方に、不思議と惹きつけられるのかもしれませんね。
⑪安田イズムの結晶 小冊子「源流」とは?
安田隆夫氏のビジネス論をテーマとする記事に度々登場する「源流」という小冊子。ここには、創業者である安田氏が社員に向けた行動規範がまとめられているそうです。
源流は2011年に初版が発行され、改訂を重ねて現在は改定新版(第4版)だ。吉田氏は会長室長として初版を編さんする過程をつぶさに見てきた。「とにかく膨大な時間を使って、安田が一字一句書いていった。言葉を極めて重要視する経営者である安田の気迫が詰まっているから、初めて開いたとき、本当にすごいものができたな、と思った」と吉田氏は振り返る。
引用元:https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00096/091500146/
「まるで本人と会話しているかのよう」と「源流」について語る吉田氏。それだけ、安田氏の息づくような経営論がぎっしりと詰まっているということでしょう。
一方で、ドン・キホーテでは社員個人が主体的に動けるよう現場の権利を委譲しています。つまり、本来であれば、社員は「源流」に頼らなくとも現場を指揮出来る権限を所有しているのです。それなのに何故、一冊の小冊子にこだわるのでしょう?
まず、「源流」の中身は至ってシンプルです。
重要なのは、企業原理である「顧客最優先主義」を遵守するための規範が徹底されている点です。例えば、経営理念には「高い志」「ワクワク・ドキドキ」といった一見感情的とも読み取れる言葉が記載されていますが、続く御法度五箇条には「公私混同の禁止」「中傷の禁止」といった現実的な内容がつらなり、ここから、権利とワガママを履き違えず節制することこそ顧客最優先主義を貫く上で最大の近道である旨を刻みつけることこそ「源流」の役割であることが窺えます。
⑫吉田直樹社長から見た安田像について
創業者の安田(=PPIH創業会長兼最高顧問・安田隆夫氏)とは、コンサルティング会社を経営している時に出会いました。1代でPPIHを築き上げた経営者として尊敬していましたが、同時に童心を忘れないユニークな人柄にも強く魅かれました。
引用元:https://dime.jp/genre/1714831/
上記は、小学館が発行するライフハックマガジン「DIME」にて、2424年2月のWEB記事に掲載されたPPIH社長の吉田氏へのインタビューから引用した一文です。ちなみに、入社のきっかけは安田氏からの熱烈なスカウトで、「今の仕事より、ドンキのほうがいいよ」という電話を毎晩もらったというから、ものすごい惚れ込みようだなと、思わず唸ってしまいました。
記事をざっと読んだのですが、一貫して安田氏のPPIH、そして社員への態度は変わりません。吉田氏に対し「今までスポットライトの当たっていなかった人こそ、ドンキという舞台で輝いてくれよ」と言い、30年目の目標も引き続き「顧客至上主義」を掲げる様子からは、安田氏の徹底ぶりが窺えます。
記事の最後で「組織は人の集まり」と言った吉田氏は、リーダーとして社員を引っ張っていくことは、社員ひとりひとりの気持ちや関係性と向き合い続けていくことだと語りかけてる、その言葉の端々には、創業以来人との繋がりによってビジネスを拡大させてきた安田氏の影響力が垣間見えた気がしました。
⑬ゲン担ぎには一切頼らない安田流必勝法とは?
職安通り一帯は今でこそ、我が国最大級のコリアン商業タウンとして栄えているが、当社が進出した当初は“ちょっと怖いエリア”で、当時の流通業界の常識からすれば、誰もが出店を尻込みするような街区だった。
引用元:https://bunshun.jp/articles/-/71379?page=2
過去には古着屋やディープな商品を扱う店舗で賑わっていた下北沢も、都市開発によって見事に整備され、クリーンな街へと生まれ変わりつつある昨今。あのディープさを懐かしむ一方で、危険と隣り合わせの状況のなかドン・キホーテを開店し地域に根付かせていったこと、街の変化とともに営業をつづけてきたことを想像し、どのような思いで安田氏がここに賭けたのか、非常に興味が湧いてきました。
私はそうしたゲン担ぎは、一切やらない主義である。姓名判断だとか、風水、四柱推命、手相などの類も、全く気にかけない。
有名企業の社長が、じつは占いに足繁く通い今後の方針を占い師に委ねているという話はよく耳にするけれど、運命論を全否定する経営者の存在は、上記の記事を詠むまでほとんど知りませんでした。
この話が本当なら、かつては「ちょっと怖いエリア」だったところに店舗を置くことを決めたのも、スピリチュアルな何かに委ねた訳ではなく、ただ経営者としての着眼点を信じたという非常にシビアなジャッジが影響しているようです。
「安田隆夫」「ドン・キホーテ」について世間の疑問をまとめてみた
「安田隆夫=ドン・キホーテの創設者にして経営者」という方程式は、日本経済や企業について興味関心やある程度の知識があればご存知でしょう。…しかし、ドン・キホーテの前身である泥棒市場が開店したのは1978年、そしてドン・キホーテ第一号店が開店したのは1989年と、既に30年以上の年月が経過しています…。
今や、若者にとっては日常の一部であるドン・キホーテですが、その「はじまり」を正確に把握する機会は、少しずつですが減少しているのかもしれません。しかし、以下の疑問がネット上で目立つ様子から推測するに、「ドン・キホーテや安田隆夫関連の情報は気になるけど、どう調べたらいいか見当がつかない」という声があがっているのも事実のようです。
ここでは、ネット上に存在するドン・キホーテや安田氏関連の疑問への情報提供、もしくは情報収集のヒントとなる内容をまとめていきますので、既によく知っているという方も、よく知らないしリサーチ方法が分からないという方も、ご一読いただければ幸いです!
ネット上の疑問一覧
- ドン・キホーテの経営者は誰?
- ドン・キホーテを店舗名にした理由
- ドンペンの作者は誰?
- ドン・キホーテ発祥の地はどこ?
- ドン・キホーテの本社はどこ?
- ドン・キホーテの支社長は誰?
ドン・キホーテの経営者は誰?
まず注意すべきは、「安田隆夫」でGoogle検索をかけた際表示される会社概要が株式会社ドン・キホーテのものであるという点です。安田氏は2015年にドン・キホーテの経営から退き、海外展開を機に一度復帰されましたが、その後、新しく立ち上げたPPIHの取締役(非常勤)に就任しました。以降、連結子会社となった株式会社ドン・キホーテのほうは吉田直樹氏が舵取りを行っているようです。
PPIH立ち上げの目的は、恐らく「事業の拡大」でしょう。早くから独自路線を独走してきたドン・キホーテの経営は、「個性的な店舗」という誰が見ても強力な武器を一つ育て上げることで、ある意味完成されてしまったのではないでしょうか。しかし、その後安田氏が海外事業を手掛けられたように、消費者のニーズを読み時代の波に乗るためには、異なる方向から風穴を開ける必要があります。その基盤づくりとしてPPIHは設立されたのでは。
以上については、「ドン・キホーテの起点になったエピソード」に詳細をまとめてありますので、よろしければご一読下さい。
ドン・キホーテを店舗名にした理由
店舗名の由来については、PPIH公式サイトの質問ページに記載されていたので、そこから引用しました。
スペインの文豪「セルバンテス」の名作にちなんで名付けたものです。行動的理想主義者であり、既成の常識や権威に屈しないドン・キホーテのように、新しい流通業態を創造したいという願いを込めています。
…そもそも、「ドン・キホーテ」はタイトルのみ知っていたとしても物語まではなんとも…という方は多いと思うので、以下に筋書きを引用したものも合わせて記載しました。
(一部省略)騎士道小説を耽読して妄想にとらわれた郷士アロンソ・キハーダが,この世の不正を正そうと,みずから遍歴の騎士になってドン・キホーテを名のり,老馬ロシナンテにまたがり,現実主義的なサンチョ・パンサを従者に仕立てて冒険と失敗の旅を続ける長編小説。
騎士道小説の登場人物のような活躍を夢見たアロソンの行動は一見すると幼稚ですが、実際にドン・キホーテを名乗り「世の不正を正そうと」「冒険と失敗の旅を続ける」姿には、見習うべきことが数多く詰まっています。
現実的に行動するだけではなく、理想を夢見ることこそ新しいビジネスを生み出す場として相応しい…そのような思いを込めて店舗名を名づけたのでしょう。
ドンペンの作者は誰?
「ドンペン」についてはこの記事の導入部分に画像を貼り付けておきましたが、皆さん日常的に街中でこの「青いペンギン」に出くわしている筈。
(この記事を書きながら、あらためて青いペンギンに遭遇した頻度について振り返ってみたところ、とりあえず繁華街では高確率で目にしていますね。それはつまり、ドン・キホーテの店舗数の多さと、それを感じさせないくらい日常に溶け込んでいる存在という証拠なのでしょうが…)
さて、肝心のドンペンの作者についてですが、Googleで検索したところ以下のTweetが表示されました。
なんと…当初のマスコットキャラクターは、店名の由来にもなった物語に登場するロバだったとか?!これは非常にレアな情報ですね…。この事実もロバの存在も把握している方は恐らく少ないでしょう。
そして残念ながら、ドンペンの作者名までは判明しませんでしたが、以外な事実が発覚した結果となりましたね。
ドン・キホーテ発祥の地はどこ?
以上の疑問の意味について、単純に捉えると「ドン・キホーテの第一号店」ですが、そもそも安田氏はドン・キホーテの前身として別名称の店舗を手掛けていたため、質問者の意図はそちらの可能性も無きにしも非ず…。
とりあえず、まずは「ドン・キホーテの第一号店」という問いの回答ですが、記事上部の「安田隆夫氏の経歴」に「1989年 第一号店であるドン・キホーテ府中店を開店」と記載しました。
さて、ドン・キホーテの前身について更に探っていくと、こちらも経歴に記載済みですが、「泥棒市場」「株式会社ジャスト」が当てはまります。
泥棒市場といえば、現在のドン・キホーテの武器である「圧縮陳列」「POP洪水」誕生の地でもあります。以下記事によると、当時ワケアリ商品を大量に仕入れ販売していた安田氏は、店内に収まり切らないダンボールを天井高く積み上げ、中身を説明する苦肉の策として「もしかしたら書けないかもしれないボールペン1本10円!」という、なんともユニークなPOPを貼り付けていたそうです。
参考元:https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1808/13/news015_2.html
自分にとっては不要なモノでも、誰かにとっては有用かもしれない…そんな意外な気付きと、ブラックユーモアが絶妙に合わさった空間が、当時の消費者に大ウケしたのでしょう。
その後、卸売販売・小売販売を行うため「株式会社ジャスト」を杉並区に設立。こちらは現株式会社PPIHの大元に当たります。公式の経歴に掲載された写真を見るに、泥棒市場の店名にもジャストの名がある当たり、当初から安田氏の脳内には「泥棒市場から独自の流通ルートを発展させていく」という構想が既にあったのかもしれません。
ドン・キホーテの本社はどこ?
こちらは「ドン・キホーテの起点になったエピソード」にも記載しましたが、本社であるPPIHは東京都目黒区青葉台にあります。Googleの検索結果を確認したところ表示される情報に特に問題はなかったので、一般層にもある程度正しく認知されていると考えて良いでしょう。
補足するため、以下に本社への地図が掲載された公式サイトURLを貼り付けておきます。
https://ppih.co.jp/corp/group/donki/address.html
Google Mapで確認すればPPIHの場所をよりリアルに体感できるので、「すこし興味がある企業の本社所在地をこの目で見てみる」というのも新たな発見があってなかなかおもしろいと思います。
…さて、ここで気になるのが、何故本社所在地を目黒区青葉台にしたか、という点です。公式サイトには最寄り駅から10分と記載されているため、出社のしやすさや立地的な意味で使いやすい、というのは最初に浮かびましたが、ほかにも理由があるのでしょうか…?
ちなみに隣接するのは渋谷区です。渋谷区といえば「MEGAドン・キホーテ渋谷本店」という大型店舗があります。MEGAドン・キホーテ目当てに渋谷へ行ったり、もしくは遊びついでに日用品を買い足していく、というユーザーは恐らく多いはずです。
推測ですが、これが理由のひとつではないでしょうか?人が集まりやすい場所に大型店舗を置き、消費者ニーズを付かず離れずの場所で観測するには、「目黒」という場所が最適だと安田氏は考えたのかもしれません。
ドン・キホーテの支社長は誰?
以上の疑問について、まずは2023年3月に発表された関連記事の概要を確認していきましょう。
総菜のカネ美食品(名古屋市)は20日、園部明義社長(55)が代表権のない会長に退き、現ドン・キホーテMEGA東海関西第1支社ミリオンスター支社長の寺山雅也氏(48)が社長に就く人事を発表した。
引用元:https://tinyurl.com/265uu9yp
上記記事下部に寺山氏の経歴が記載されていました。概要は以下の通り。
1999 年3月ドン・キホーテ入社。一宮店長、浜松可美店長や東海支社統括店長、北陸支社長などを歴任した。
上記の通りであれば、「ドン・キホーテの支社長は誰?」という疑問に対する回答は寺山氏で問題ないでしょう。
ちなみに、寺山氏がカネキ美食品の社長に就任した目的は「業務提携するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)との協業をさらに進めるため」であり、さらに「4月1日付でカネミ食品執行役員社長補佐に就任予定」だそうです。
ドン・キホーテの口コミ・評判から見る強み

さて、これまで安田隆夫氏の著書や経歴からドン・キホーテの強みを探っていましたが、利用者の実際の口コミからドン・キホーテの強みを探っていきましょう。
例えばこんな口コミを発見しました。
宝さがし気分が味わえるので、ドンキホーテは大好きです。でも、渋谷のショップはしばらく行ってないので、また行きたいですね。
場所柄、若い人の利用が多いです。ですので、商品も、あんまり生活感のあるモノよりも、ファッション関係のモノが多いように感じます。
渋谷の店舗について記載されていますが、やはり土地柄に応じて何がアミューズメントになるのか、ということはしっかり抑えた上で商品ラインアップを揃えているようですね。
渋谷店になると原宿なども近いので風変わりな商品を揃えることで売上が上がるのですね。
ドンキホーテ社はディスカウントストアですので、大量仕入れ、スケールメリットを活かした値下げがあるはずなので、高級至高の街に展開するよりも若者が集まる土地に出店するほうが効率は良いように感じます。
しかし、日本でも屈指の高級住宅地である白金台にもドンキは店舗を出店しております。アミューズメントを重要視する安田氏はどのような戦略を選択したのでしょうか。
白金台のドンキホーテについての口コミがこちらです。
24時間営業。土曜深夜、駐車場は一杯で入れず。しかし、
近くの夜中は無料で止められる路上の枠線(正式名称なんだろ)に止めることができるから良い。白を基調とした開放的な造り。上にはプラチナドンペン君が回ってる。
流れてる音楽も並んでる商品も雰囲気も他のドンキと変わらないっちゃ変わらない。違う点と言ったら、松坂牛を扱う精肉店があることや新鮮野菜を数多く扱っているところ、そして200円+税の激安弁当が売ってるところか。夜中だと松坂牛は半額で販売されている。
お客さん、身なりが良い人がちらほら。この辺りも他では見られない点か。
やはりというべきか、高級住宅街である白金台では渋谷店とは違った店舗になっているようです。
松阪牛を販売しているドンキとはあまりイメージがつきませんが、この店舗に訪れる人はなにか良いものないかな、面白いものがないかな、と店を訪れるのでしょう。
ドンキ以外の小売業について恐らく白金台にはたくさんあるはずですので、競合ひしめく中、ドンキが選ばれる様な戦略というのがこの成長の大きな要因の一つになっているようですね。
安田氏独自の経営戦略

2020年も継続して増収・増益を続け、輝かしい業績を記録し続けているドンキホーテですが、その根底には安田氏の独自の経営戦略・会社運営手法があるのかもしれません。
安田氏の経営手腕についての調査を行ったところ2008年のPresident Onlineの記事に
ドン・キホーテは35歳で従業員の年収は3倍もの差がでることがあるとの記載がございました。
ドン・キホーテでは半俸制を採用しており、成果に応じた昇進・昇給が大胆に行われる仕組みになっているようです。能力に応じて年令に関係なく昇進昇格を行い、報酬格差も大きく設定することにより「競育」と安田氏が表現する状態が作り出せるとのことです。
また、本人のやる気を出させるための手法として「どういうやり方で売上を上げるかどうかは本人の裁量に任せ、上司は口をあえて出さない」という「権限移譲」も進んでいるそうです。
このように、より売上利益を出すための取り組みと、結果に対する正当な評価制度を
整えることにより強い組織を作り上げることができているのかもしれませんね。
安田氏の最新情報

安田氏は会社経営以外にも様々な活動に尽力しています。それらの最新情報をご紹介します。随時更新していきますので注目してみてください。
緊急支援金給付
安田氏が設立した公益財団法人安田奨学財団は、この度のコロナ禍で苦しむ日本人大学生・大学院生に向けて緊急支援金を給付するようです。
コロナウイルスの影響により、日本人大学生がアルバイトもままならない事による経済困窮で退学を検討しなければならないという状況を鑑みて、緊急支援に乗り出したとのことです。詳細は下記のとおりです。
支援金の特徴
- 本財団では対象者の選考は行いません。対象者が支援金を必要としているか否かは大学側の判断とします
- 支援金は給付とし、返済の義務はありません
- 対象者の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします
- 他の奨学金等との併給についての制限はありません
応募資格
新型コロナウイルス禍により経済的に学業継続が困難な状況に瀕していると大学が認めた日本人大学生もしくは大学院生
採用人数
各大学10名以内(全大学合計100名以内)
支援金額と方法
- 支援金額:30万円(5万円×6か月間)
- 支援の期間:6か月間支援の方法:2020年8月~2021年1月までの毎月末に月額5万円を直接本人に支援します
日本の将来を担う、勉強を続ける大学生・大学院生に向けた安田氏の期待と思いやりを感じたリリースでした。
海外市場への挑戦
10月23日、ドン・キホーテを運営するPPIHから
「Pan Pacific International Club(通称PPIC)」を発足する旨が発表されました。
説明によると、
PPICは日本の農水畜産物輸出拡大を目的に、生産者とPPIHグループの会員で構成された組織
引用元:https://www.ppihgroup.com/ppic/
を意味するそうです。
東京・帝国ホテルでの発足会にて安田氏自ら「最後の社会的使命」と語るPPICの活動とは具体的にどのようなものなのでしょう?
PPICの目的
- 国産農水畜産物の成長促進エンジンの安定化
- 安定した出荷先の確保
- 出荷価格が市場や天候に左右される課題の解消
PPICの活動とメリット
- 会員は海外店舗出荷の商談に参加可能
- 商品出荷を継続することで安定化が図れる
- PPIHのPOSデータ(※)を活用し海外のマーケット情報を提供
- ↑により作付・製造計画のサポートが受けられる
※「Point Of Sales=販売時点」の略で、店のレジでバーコードの情報が読み取られ、商品の支払いが終了した時点のデータを指す
対象
- 生鮮食品に携わる事業者・団体
退任後シンガポールに移住した安田氏は、日本の食品が現地の一般的な価格の2~4倍で販売されている現実を目の当たりにし、またその裏に「ハーモニープライス」というカラクリが潜んでいることを知ると、これを打破すべくPPIC発足へ動き出したそうです。
2017年にASEAN地域に初進出して以降、海外進出を加速させているPPIHは、新型コロナウイルス流行下にあっても右肩上がりの業績が見込まれています。
このままいけば、間違いなくPPICの取り組みは業績拡大に貢献するだけではなく、
日本に留まらず世界中が抱える輸出、食品問題を解決する糸口となり得るかもしれません。
その後について
以下、2022年8月中旬に発表された、ドン・キホーテシンガポール店に関する最新記事です。
シンガポールの人口は545万人。そんなコンパクトな国に進出した「ドンキ」が、わずか5年足らずで12店舗まで増える人気ぶりだ。今回訪れたのは、シンガポール東部に位置するショッピングモール「タンピネスワン」の中に入居する店舗。
引用元:
https://www.esquire.com/jp/culture/column/a40738133/dol-don-quijote-is-very-popular-in-singapore/
記事によると、まず驚かされたのは店内の様子が日本とは明らかに違う点。日本のドン・キホーテといえば、店中隙間なく商品で埋め尽くされた光景がお馴染みですが、タンピネスワン内の店舗は入口近くに生鮮食品が置かれているなど、まるでスーパーのようだと記載されています。
…確かに、店内の写真を見ると、そこに写っているのは「我々が普段利用しているふつうのスーパー」です。ちなみに商品は日本の食品が中心。
近所に住む若いカップルはほぼ毎日通い詰めては、菓子を購入するほか、時にはウィンドウショッピングをするだけでも充分たのしめるとインタビューに答えていました。「見ているだけで飽きない」というのは、日本の店舗と共通している部分であり、恐らく安田氏も新店舗プロデュースの際は気を配っているものと推測します。
ドン・キホーテのシンガポール進出をYouTubeでチェックしてみた!
シンガポールでのドン・キホーテの活躍ぶりについて特集したYouTube動画を発見しました!こちら、安田氏への直撃インタビューも盛り込まれたなんとも豪華な内容です。
さっそく、「アメリカはなんとしてもものにしたい」という気合の入った言葉で野望を語る安田氏が登場するという、非常にエネルギッシュなOPからスタート。
次に、安田氏へのインタビュー前に、シンガポールはオーチャードセントラル店のドン・キホーテを視察。入店してすぐ「ドンドンドン・ドンキ~♪」というお馴染みのBGMが流れているあたり、日本人にとって身近な存在という価値観は国が変わってもどうやら同じのようですね。さて、肝心の品揃えですが……画面は高級肉、寿司を映し、そしてそれら商品に対する出演YouTuberは「こんなイケてる日本食スーパーは他にない」と豊富なラインナップを大絶賛。個人的には「日本のスーパーより良い」というコメントが印象的でした。ちなみに、シンガポール店社長によると、客層は95%地元民なのだとか。地元密着型店舗によって住民の生活に根ざした店づくりをするドン・キホーテの得意技はここでも健在!ですね。
日本と大きく異なる点は店内の広さやフードコート的なエリアが併設されている点でしょうか。日本の所狭しと商品が陳列されているスタイルとは違い、出演YouTuberが言うように「食のテーマパーク」な店内は広くエリアごとにテーマがきちんと整理整頓されている様子から、「シンガポールに新たなアミューズメントをつくろう」という気概を感じました。
個人的に印象深かったのは、店内で購入したおにぎりを食べている場面です。
「元々は精米所で作った精白米をどのようにして売っていこうと。そこでお客様に食べていただくために、有料試食としておにぎりを販売した。」
まず「有料試食」という言葉をはじめて耳にしました。調べてみると、ブライダルフェアやフード系のイベント等で有料試食が提供されているようです。
消費者にとっては日常の風景のなかで「試食=無料」という固定概念が極端に刷り込まれていますが、冷静に考えてみると、そもそも試食が100%無料である必要はどこにも無いんですよね……。このあたりは、「お客様は神様です」という国民性も大きく関係しているのでしょうが、消費者に対し良質なサービスを提供する分正当な対価を求めるというベーシックな需要と供給は、今後のビジネス界を生き抜く上で重要なポイントになっていくでしょうね。
もちろん、海外の日本食ブームがまだまだ健在という背景も、ドン・キホーテのシンガポール店の人気に一役買っていることは恐らく間違いないでしょうが、安田氏による「日本食をやるうえでコメを売らないと成り立たない」という考えもまた、基本に忠実だからこそキラリと光るなにかが新たなビジネスを生むのかもしれません。
そんな安田氏がシンガポール店のスタッフに向けて頻繁にくちにしている言葉は「なにか新しいことを仕掛けているか?」だそうです。
この問いかけが意味するところは、コロナを通して既存の価値基準がくずれた今だからこそ「失敗を恐れず積極的に新しいことにチャレンジしていく心持ち」の重要性を伝えようとしているのだとか。
さて、動画中盤で登場した安田氏に向けて最初にされた質問は「おにぎり戦略」について。安田氏いわく、「試行錯誤によって美味しくできあがったシンガポール店のおにぎりは必然的に値段が上がってしまったため恐らく日本では売れないだろけど、そういう商品はシンガポールのお客様には買ってもらえる」「如何に海外で日本のコメを広げていけるかが重要」と、おにぎり戦略の舞台裏での努力と独自の経済戦略について論じていました。
現在、日本は飽食の時代と呼ばれていますが、たしかにここ数10年は平均的な生活さえしていれば食事には事欠かない生活が主流となりつつあります。その「平均値」は一体どういうものなのか、そもそもそこからこぼれ落ちる人が不可視化されている現状を飽食と呼ぶべきか、といった課題が山積みな一方で、そもそも「コメが余っている」というのももっと問題視されるべきだと思いますが、このような社会問題に対しても独自の理論でメスを入れようとしているからこそ、安田氏はスタッフに向けて「新しい仕掛け」を説くのでしょう。
さらに安田氏の「コメ談義」はつづきます。安田氏曰く、「タイで日本米が売れている。コメが最も安い国で日本米が売れるなんて、それこそアラブで石油が売れるのと同じ(笑)」と、冗談交じりに日本米が世界で高く評価されている現状を語っていました。
安田氏がこれほど熱を込めて語る理由は、日本に住んでいる国民にとって最も身近なコメの魅力が理解されていないことを心底もったいないと嘆いているからこそなのでは。日本米の真の魅力を伝えたくて、多少値段が上がったとしても「わざわざ精米したてのコメをおにぎりにする」という手間を惜しまず販売するという賭けに出たようです。
日本に余っているコメを再利用し、「日本米の魅力を最大限伝えるアイディアを生み出す」ことに尽力する姿は、「もったいない精神をビジネス化」していた泥棒市場の頃となにも変わらないなぁと思わせてくれるものでした。
ちなみに、安田氏がコメ戦法のため目をつけたのはおにぎりだけではありません。次のビジネスチャンスは、海外でも大人気の日本食「寿司」です!昨今、日本のオーソドックスな形を飛び出し、あちらこちらの国で自由な解釈によって「グローバルな寿司」が誕生しているからこそ、絶対的な可能性を感じていると安田氏は語ります。
社名変更にこめられた覚悟
2019年に商号をPPIHへと変更したことは上記しましたが、それまでは長年にわたり同社
が展開するディスカウントショップ「ドン・キホーテ」を屋号として使用してきました。
商品が詰め込まれた陳列棚が消費者を圧倒する様子が人気を呼んだドン・キホーテですが、このようなスタイルが一般層に認識されるまでには困難な道のりがあったことは、安田
氏の経歴を読んでいただければ自ずと想像できるでしょう。
様々な歴史がつまった「ドン・キホーテ」という社名は、恐らく安田氏にとって言葉では
言い表せないほど大切なものであるはず…それを変えるまでに、一体どのような覚悟を決
めたのでしょうか?
「“ドンキ”を海外へ 安田隆夫会長が社名変更に込めた覚悟」では、社名変更のキッカケに
ついて次のように記されています。
国内の消費市場は、人口の減少に伴い縮小していくのは明らかだ。今、何をしなければならないかを突き詰めた結果、海外での起業を選択し、安田自身がその先頭に立った。PPIHへの社名変更を「第2の創業」と位置付けている。
引用元:https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/280558
東京での深夜営業からスタートした安田氏とドン・キホーテにとって、海外市場はまさに
未知の領域ですよね…それでも、企業の生存をかけて敢えて茨の道を突き進むという選択
の裏には、流通のあり方を変えたいという強い思いがあったに違いありません。
安田隆夫氏が「創業者メッセージ」にこめた思いとは?
安田氏の経営方針やビジネス感覚をある程度知りたいのであれば、関連書籍のほか検索結
果に表示されるインタビュー記事等を参考にするのが、最適且つ最短の解決方法だと明言
できます。
例えば以下URLにはドン・キホーテ創業にこめた安田氏の思いが掲載されており、ここか
ら創業までの経歴や経緯だけではなく、市場の変遷との向き合い方なども把握できるため、過去~現在の流れを追う資料としても活用できるのではないでしょうか?
https://ppih.co.jp/corp/founder/
記事には次の一文があります。
また、意外に思われるかもしれませんが、当社は攻撃以上に守備を重視する企業です。具体的には「攻撃3割、守備7割」という当社なりの黄金比でポートフォリオを増やし、加えて独自の「複利経営」を行ってきたことも、当社がドン・キホーテ1号開業以来の連続増収増益という金字塔を打ち立てられた直接要因と自負いたしております。
安田氏がナイトマーケットの可能性に気づいた泥棒市場、陳列棚にあふれんばかりの商品
ディスプレイ、海外市場への挑戦など、攻撃重視のビジネス展開を貫いているかと思いき
や、チャンスや利益の窓口を最大限ひろげるため敢えて複利経営という守りに入る姿勢か
ら、必要に応じしっかり武器と盾の使い方を変えることで、時代とニーズに適した形を提
供できていることが推測されます。
12月よりネット動画専用テレビ発売開始、安田氏とドン・キホーテの狙いとは?
12月10日より、ドン・キホーテにて「You Tube・Netflix・Amazonなど動画配信サービス専用テレビ」が発売開始されたそうです。
こちら上記の通り、大きな特徴はネット接続が可能な点。…しかしチューナーが無く、地デジ等テレビ番組が一切見れないという、なんともシンプル・イズ・ベストそのまんまの商品です。
プレスリリースでは「テレビのようでテレビじゃない!!」「ついに作ってしまった!」とアピールされています。
引用元:https://news.nicovideo.jp/watch/nw10309023
以下に大きさと価格をまとめました。
- 24インチ:2万1,780円(税込)
- 42インチ:3万2780円(税込)
リーズナブル且つシンプルな価格設定がドンキらしさをあらわしていますね。引用元の記事によると、現在このテレビはSNS上で話題を呼び、試しに購入してみようという消費者が増加傾向にあるそうです。
これぞまさに安田氏独自のコンセプト「CV+D+A(利便さ、値下げ・安さ、たのしみ)」を体現するだけではなく、「必要だから行く<面白いから行く」をテーマに掲げるドン・キホーテならではの魅力的な販売方法なのでは?
今後も安田氏がどのようなアイディアを打ち出してくるのか、待ち遠しいですね!
ドン・キホーテから女性向けブランド誕生!「女性が求めるもの」を追求する姿勢に影響を与えたのは安田氏の◯◯な姿勢から?!
2022年10月後半、ドン・キホーテの全国系列店舗に、初の女性向けブランド、その名も「me&do」の商品が陳列されたそうです。
女性向けブランドといえば、実際は企画開発のメインに女性社員が関わっておらず、男性社員主導で話しがすすめられた結果、女性の購買欲センサーがビクトもしないだけではなく、「むしろ“女性らしさ”を押し付けるメッセージ性が強化されていて気味が悪い」と批判を受ける、なんて出来事はここ最近頻繁に耳にします。
…一方、「me&do」はどのようなコンセプトかといえば、そこからは安田氏が最も重視していた「現場主義」を彷彿とさせる姿勢が垣間見えました。
まずは男性社員が企画開発した商品を女性目線でダメ出すことからスタート。素材やパッケージ、成分に至るまで徹底的に議論を交わし、女性の意見を反映した、女性の悩みやニーズに寄り添った商品が生まれた。
引用元:https://retailguide.tokubai.co.jp/trend/28144/
引用元に掲載された商品の一部「はしれるパンプス」など、女性の「リアルな」生活上の悩みと「これさえあればなんとかなるのに!」という必死の願いに本気で向き合った結果誕生した新たなブランドは、まさに「新しいカタチの現場主義の誕生」でもあるのではないでしょうか。
「道玄坂通 dogenzaka-dori」開業!開通式には安田氏も出席
2023年8月、PPIH初となる複合施設が道玄坂に開業しました。その名も「道玄坂通 dogenzaka-dori」。
24日に開催された開通式には安田氏も出席し、「渋谷駅を中心に素晴らしい施設がたくさんありますが、坂の上には坂の上のまた違う世界がある」と、初の試みに道玄坂を選んだ理由を説明。
道玄坂がある渋谷は、「道玄坂に道(みち)を拓く。上質な日常と刺激的な非日常が交差する」というコンセプトがあらわすように、現在再開発計画に沿って様々な新しい空間が出現している真っ最中です。こちらも再開発中の渋谷駅から徒歩5分の立地に建てられた「道玄坂通 dogenzaka-dori」は、地下1~地上28階からなるフロア内に、ショップ・オフィスフロア・ホテルが入居し、国内外の誘客を目的とした新たな「にぎわいの拠点」という役割を担っているそうです。
(中略)4つの出入口から施設内を通り抜けて渋谷の街を行き来(堂々巡り)できる構造となっている。これに由来して、通称は「ドードー」。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/4bede6c168008886a390f0770ce3fe8a4daaaa03
綿密に構成されたコンセプトが新たな「にぎわいの拠点」として今後どのような化学反応を道玄坂に生み出していくのか……非常にたのしみですね!
既刊紹介
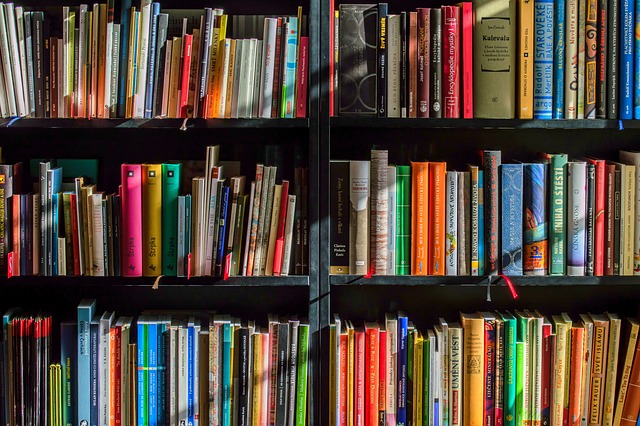
安田氏の生い立ち等、人生エピソードについては、これまでに出版された書籍にも詳しく記載されています。
ここでは、安田氏の書籍をご紹介しましょう。
安売り王一代 私の「ドン・キホーテ」人生
こちら、2015年に文集新書より出版されました。
紹介文には「驚異の“26期連続増収増益”ドンキホーテはいかにして生まれたか?」と記載されているので、恐らくドン・キホーテが成長するまでのエピソードや安田氏のユニークな経験と経営論などが主な内容なのでしょう。
特に印象的なのは、夜中に荷解きをしていた際、飲み会帰りのサラリーマンに話しかけられたことで安田氏が得たとあるヒントにまつわるエピソードです。
消費者の生活に根ざした商品を販売するドン・キホーテの生みの親ならではのエピソード、という印象を受けました。
情熱商人 ドン・キホーテ創業者の革命的小売経営論
こちら、2013年に月泉博氏との共著として出版されました。
ドン・キホーテ設立までとそこに関わる安田氏の経験談がメインの一冊となっています。
紹介文にはこう書かれています。
ドン・キホーテ創業者安田隆夫氏が、三十有余年にわたる商業者としての
体験の中で会得した小売業の極意と本質
また、「若き商人への熱いメッセージ」という一文についても注目したいです。
SNSやIT技術を活用すれば学生でも起業できてしまう時代に生きる若者にとって、安田氏のやり方は多少奇妙にうつるでしょうが、
ドン・キホーテや消費者目線にかける情熱を知れば、そこから多くを学べる…というメッセージが込められた一冊なのかもしれません。
ドン・キホーテ 闘魂経営
こちら、「情熱商人 ドン・キホーテ創業者の革命的小売経営論」と同様、月泉氏との共著として2005年に徳間書店より出版されました。
流通界の風雲児と呼ばれる安田氏が、数々の経営危機やバッシング等ドン底状態を如何にして乗り越えてきたのか、そこに込められたひたむきな「はらわた力」を読み解く内容になっているようです。
昨今の就職・転職の場ではスキルばかりが重視される傾向にあります。しかしそれ以上に何かを最後までやり抜くには、諦めないための「人間力」が不可欠であることを、きっとこの著書から学べるでしょう。
ドン.キホーテの「4次元」ビジネス―新業態創造への闘い
こちら、2000年に広美出版事業部より出版されました。
バブル崩壊後の景気低迷、人員削減、リストラ…逆境の時代を「常識破壊企業」と呼ばれたドン・キホーテはどう生き抜いてきたか、何故驚異的な成長が実現したのか、数々の謎の答えや独自の方法論が記載されています。
不安定な状況を乗り越えるには、古い常識を覆し、新しい仕組みをつくらなければならず、だからこそ、敢えて逆境を乗り越え道を切り開かんとする安田氏の姿勢から、経営論だけではく人間力も学べるでしょう。
流通革命への破天荒な挑戦!―ビジネスの原点は「常識」を疑うことだ
こちら、1997年に広美出版事業部より出版されました。以下説明文です。
話題のスーパーコンビニ「ドン・キホーテ」はなぜ驚異的成長を実現できたのか。創業者が初めて公開する成功への人間学と実践手法。ビジネス自己実現を可能にする超発想法。
上記説明文を見るに、ビジネス書というより、自己啓発書の方が近いかもしれません。
ほかの著書からも安田氏の人間力を学ぶことは可能ですが、『流通革命への破天荒な挑戦』を読めば、仕事と向き合うための精神テクニックをより具体的に掴めるでしょう。
以上、これまでに出版された安田氏の著書計5冊を紹介しました。
例えば、以下の悩みを抱えた方々に非常に最適な内容が記されています。
- 0からビジネスを立ち上げるため経営者の経験談に目を通したい方
- 現在手掛けているビジネスが下降気味のため突破口となるヒントが欲しい方
もちろん、多くの方々に安田氏の著書を手に取って欲しいところではあるものの、特に経営に関する知識や経験が乏しい方にオススメしたいですね。
何故なら、安田氏自身が経営初心者でありながら「ドン・キホーテ」を一代で築き上げたからに他ありません。
インタビュー記事

安田氏の経営論や人柄を理解するには、「既刊紹介」に掲載した著書を読む以外に、イン
タビュー記事に目を通す方法をオススメしたいです。
ネットで検索すれば安田氏のインタビュー記事を無料で読めるので、著書購入の前に事前
知識として取り入れておくのも良いでしょう。
以下、安田氏のインタビュー記事が掲載されたURLと内容をまとめたので、是非参考にし
てみてください。
常識と戦い続け、流通革命に挑む / ドン・キホーテ
参考URL:https://www.dreamgate.gr.jp/contents/case/company/32171
こちら、2008年1月に「DREAM GATE」というメディアに掲載された記事です。
この記事では、アウトサイダーを地で行く青春期から、常識と戦いドン・キホーテを立ち
上げるまでの経緯がまとめられています。
特に興味深いのが、大学時代のエピソードです。
慶応という一流大学入学を機に上京した安田氏は、勉学より「働く」ことに惹かれた自身
の体験について次のように語っています。
振幅の激しいことをやっていると、ある時、振り子が真ん中に戻って、嘘のようにバランスが取れるということを、経験したような気がしますね
常識や他人の言葉に決して惑わされず、自分の道は自分で決め、苦労を厭わず突き進んで
いく安田氏の原点が垣間見える一文です。
ドンキホーテHD、米国で「持ち帰り総菜」店舗展開へ
参考URL:https://jp.reuters.com/article/retail-japan-interview-idJPKCN0HP0DZ20140930
こちら、ドン・キホーテの一部事業がアメリカ進出する旨をまとめた記事で、2014年に発行されたようです。
記事によると、買収済みのマルカイの一部店舗を活用し、日本食惣菜の持ち帰り販売に特化した店舗展開を翌年スタートする、という内容が記載されていました。
マルカイとは、2013年に買収した日系スーパーを指し、ドン・キホーテとはまた異なる新しい店舗名を冠する商店として展開するというのが、当時安田氏が思い描いていた構図になります。
当時、ドン・キホーテはハワイ・南カルフォルニアを中心に、マルカイを含めた海外展開は10数店舗に及び、安田氏は次の展開についてアメリカ本土を視野に入れつつ、アジア進出について「(海外では問屋システムがないため)多種多様な品ぞろえをすることは難しい」と述べています。
ちなみに、アジア進出についてはその後調べてみたところ、既に数店舗が展開されているだけではなく、2021年にはマレーシア出店が実施されるとのこと。
マルカイ買収、出店の目的について安田氏は「オリエンタル・モバイル・フーズと言っているが、要するに総菜・中食。米国では、それをきちんと供給している店が非常に少ない。個人でできるような屋台の店と専門的なスキルを必要とする店の中間がない」とし、「それに特化した店舗を作る」と語ったことから、海外市場ではなかなか満たせない中間的なニーズをドン・キホーテ独自のメリットで満たすことこそ真の狙いであり成長戦略のひとつなのでは…という印象を受けました。
中小企業から大企業へと生まれ変わるための絶対条件。部下への権限移譲が社長の自己表現への王道だ!
参考URL:https://leaders-file.com/interview/904/
こちら、ビジネスの第一線で活躍する経営者へのインタビュー記事が中心のWEBメディアにて2013年に掲載されたもののようです。
タイトルの通り、テーマはドン・キホーテの成長物語が中心ですが、そこには安田氏の「飾らない戦略」が鍵となっている事実がこの記事からより鮮明に見えてきました。
例えば、このような一文があります。
伸びる経営者を見極めることは難しいと思うが、ダメになっていく経営者なら、私はすぐわかる。その特徴は3つだ。
第一に見栄っ張りであり、小さな成功で、小さな虚栄心を満足させようとすること。(中略)
確かに、一定の収入額を超え、所謂成功者と呼ばれるランクまで昇りつめた人間なら、「すべて自分の努力と実力の結果だ」という慢心に溺れても無理はありません。そこから更に切磋琢磨できればまた違うのでしょうが、安田氏の言うように、「小さな虚栄を満足させ」てしまっては、その先の成長は難しいのでは…。
(中略)だが上場したときに、当社は社会的な存在になったのだから、「オレが、オレが」ではなくて現場の人たちを立てることに専念しよう、皆の応援団になろうと切り替えたのである。
企業全体がステップアップする上で重要なのは、リーダーが存在感を必要以上にアピールすることではなく、潔く下の世代にバトンを渡す姿勢を示せるかどうかであり、これこそ安田氏が掲げる「飾らない戦略」なのでしょう。
【ドンキ安田】これから日本は、さらに「ディスカウント化」する
参考URL:https://newspicks.com/news/4418057/body/
こちら、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」から2019年11月に発信された記事になります。
(会員制のため全文確認は不可能でしたが、序文だけでも非常に興味深く、また登録後一ヶ月無料キャンペーンが受けられるため、試しに利用してみては→https://newspicks.com/)
この記事は「小売の帝王が帰ってきた──。」からはじまるため、タイトル通り安田氏の復帰の真相をテーマにインタビューの様子がまとめられているのでしょう。
日本国内に留まらず、海外でも独自のビジネスを展開、その多くを成功に導いてきただけあって基盤は盤石のはずなのに、それでも前線で動こうとする安田氏がいるからこそ、この企業はまた新たなチャレンジに邁進できるのだと、「復帰」の二文字から感じとれました。
また、記事の概要には
特集の後編では、Eコマース時代の小売の未来図や、海外展開。そしてドンキの強さの根幹であるプライシングについて、たっぷりと語ってもらった。
とあるように、安田氏が思い描く今後についてもフォーカスしているため、例えばここからコロナウイルスが与えた経済への打撃をどう乗り越えていくのかというヒントを掴めるかもしれません。
現状のピンチをどうチャンスに変えるか…「継続」を選んだ安田氏にしか導けない答えがここにはあるのでしょう。
セレブの心理をくすぐります!ドンキホーテが東京・白金に実験店開業
こちら、日刊工業新聞が主催する「ニュースイッチ」にて2015年に発表されたものになり
ます。
テーマは安田氏へのインタビューというよりそのままタイトル通りなのですが、以下持論
が起点になっていると推測されるので、ドン・キホーテの経営戦略をより深堀りするには
最適かもしれません。
同社の創業会長兼最高顧問の安田隆夫氏は「小売業は地域ナンバーワンでなくてはならな
い」が持論。そのため、店舗に権限を与え、地域のニーズをくみ取る商品政策、店作りを
推進してきた。いわば今回のプラチナドンキはその経営戦略を一歩進めた店舗といえる。
ここで紹介されている「プラチナドンキ」とは、白銀台の高級住宅地に当時実験店として
開店した店舗を指します。
24時間営業なのは通常と変わらずですが、特徴的なのは、雑多に並べられた格安品に混
じる松阪牛の専門店…。
通常、家電やパーティグッズなど、バラエティに富んだ品揃えと広々とした店内がドン・
キホーテの代名詞。ですが、プラチナドンキでは敢えて食料品など消耗品に限定しながら
も、格安弁当から高級酒と幅広い価格帯の商品を取り揃えたあたり、まさに「シロガネー
ゼのニーズに特化した経営戦略」なのでしょう。
同業者だけではなく、自社店舗においても差別化を計るドン・キホーテに安田氏が今後ど
んな一手を投じるのか…非常にワクワクさせてくれる内容でした。
ドン・キホーテ創業経営者 安田隆夫「私が早期引退した理由」
参考URL:https://president.jp/articles/-/16411?page=1
「ドン・キホーテの起点になったエピソード」にて、安田氏が一度前線から退き、その後2019年に取締役として復帰した旨を記載しました。復帰するに至るまでにも新しいチャレンジによって経営の活路を開いてきた安田氏ですが、その真意は果たしてどう考えていたのでしょう?
上記インタビュー記事によると、安田氏は自らの引退を「勇退」と呼んでいたそうです。その理由を尋ねると、以下の返答がありました。
私がこれ以上、創業経営者として君臨し続ければ、会社が私に、私が会社に依存する「共依存」の状態となり、組織が硬直化する恐れがある。だから思い切って勇退することにした。
共依存状態は企業と自身の成長を留めてしまう…膠着状態をなによりも恐れ、「30年50年先も我が子(ドン・キホーテ)が繁栄しつづける」未来を本気で願うからこそ、安田氏は自ら主導権を手放す決断をしたそうです。
引退に先駆け、安田氏は社員に今後を託すべく企業理念を新たにまとめ上げ、「カリスマ経営者を必要としないビジョナリー・カンパニー」としての第一歩を踏み出しました。我が子である企業の成長を誰よりも望むからこそ敢えて一線を引き厳しく接する姿勢は、親としての愛情溢れる行為に他ありませんね。
『ドン・キホーテ創業者』安田隆夫の「現場主義と顧客最優先主義に徹して」
参考URL:https://www.zaikai.jp/articles/detail/1559
変化しつづける消費傾向に対応しようと次々に新たなチャレンジを打ち出すドン・キホーテですが、近年は海外進出に意欲的で、詳細についてはこの記事でも度々取り上げています。
ドン・キホーテが今海外事業に積極的になれるのも、恐らく安田氏が日本拠点を吉田氏に任せ、自らシンガポールに移住したことが大きいといえるのでは。現在アジアを中心に店舗を拡大させつつ、特に日本産品専門セレクトショップの経営に全力投球していると記事に記載されています。
そんな安田氏が懸念するのは円安に対する世界中の消費者の反応です。日本の丁寧且つ繊細なもの作りの姿勢が評価されたから、ではなく、単純に「円安だから」という理由で売買が成立してしまう現状について、安田氏は
「円安もそうだし、賃金も上がらず、物価も上がらない。日本のモノがどんどん安くなっているから、海外でメイド・イン・ジャパンの専門店をつくっても海外のお客様からは、何だこんなに安いのかと思われている。お客様が喜んで買っていただけるのは嬉しいが、日本人としてこれを喜んでいいのかどうかは疑問」
と記事内で不安を吐露されています。
今後、「With コロナ」が更につづいていけば、世界の経済も大きく変化していくでしょう。その時安田氏がどのような決断を下すのかが、ドン・キホーテの今後を左右する重要な「要」になるでしょう。
日本の農畜水産物は「第二の自動車産業」になる――安田隆夫(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス創業会長兼最高顧問)
参考URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/f858548ab1ed8661c7972f12a75756edb374e18e
「元々は精米所で作った精白米をどのようにして売っていこうと。そこでお客様に食べていただくために、有料試食としておにぎりを販売した。」
上記は「ドン・キホーテのシンガポール進出をYouTubeでチェックしてみた!」に記載した一文です。You Tubeチャンネルにて公開されていた動画を元に、シンガポール進出後の現状や安田氏のビジネス論をまとめていくなかで、特に目に留まった内容が「コメ談義」です。昨今の日本食ブームの立役者ともいえる日本の米が、じつは自国では売れ残ってしまっている……そんな現状の打開策として安田氏が新たに打ち出した仕掛けが、シンガポール店でのおにぎりの有料試食、というワケです。
いま日本の農畜水産物を一番海外で売っているのは、私どもではないかと思います。日本の食文化はもっと広がる可能性がある。和食のレストランもやり方を工夫すればさらに増えると思いますし、食材も同じです。日本の食品は、「第二の自動車産業」になりますよ。
インタビューによると、安田氏はコメを起爆剤とした新たな日本食ブームをスタートラインに、シンガポールにて良質な日本製品を販売するルートを開拓しようと、次なる仕掛けを構築中なのだとか。
33期連続増収増益。ドンキの強さをつくった権限委譲カルチャー
参考URL:https://forbesjapan.com/articles/detail/64663
海外の新店舗など、数々の新規事業を立ち上げつづけているドン・キホーテですが、一見これらすべてを安田氏が舵を切っているとようで、あくまでも立場は裏方に徹し、表舞台の華々しい演出は他の社員に任せているようです。
「チェーンストアは、マニュアルによってどこの店でも金太郎あめです。だからこそ同じものを安く大量に供給できるのですが、目隠しして連れてこられたらどこの会社の店かわからないくらいにみんな同じで個性がない。ならば真逆をやろうと、現場に徹底的に権限を委譲して任せることにしました。おかげでドンキの場合はすぐドンキだとわかる」
何を仕入れ、どのように現場を動かすかまで、社員個人に委ねられるというのは、新たなチャンスに恵まれた一方で、責任も重大です。「自分の発注ひとつが店の経営を左右する」と考えれば考えるほど責任感に追い詰められてしまう社員も少なくはないでしょう。
しかし、現場に一任するというのは、安田氏自身が現場の主導権を握ってばかりいてはいつまで経っても下が育たないという意味であって、なにも現場とのコミュニケーションを断絶したという訳ではありません。
「すごいね、よくやったねと普通に褒めてもいい。しかし、それ以上に『長い間一緒にやってきたけど、あなたのこういうところはすごいと思う』と本人がひそかに誇りに思っていることを指摘するのが最上級の褒め方でしょう。私は過去十数年、現場を褒めっぱなしです」
若手社員の努力を認めるにはまず、安田氏が積極的に社員個人との関わりを持たなければはじまりません。そうやって彼らの個性を現場に活かしていくことこそ、ドン・キホーテにしか出来ない権限譲渡カルチャーなのでしょう。
その他
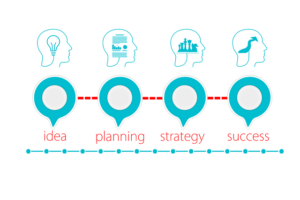
以下、書籍以外にも、安田氏独自の経営理念を記した商品が販売された記録がネット上に残っているので、そちらの情報を紹介していきます。
お客様のナマの声”が快進撃の原動力 ドン・キホーテお客様との「一体感経営」CD
参考URL:https://www.jmca.jp/prod/1077
こちらの情報が掲載されている「日本経営合理化協会」(https://www.jmca.jp/)とは、中小企業の成長発展を目的に、セミナー開催や経営者が執筆した書籍等の販売を行う企業のようです。そこでドン・キホーテの名前を冠したCDとビデオテープが販売されていまして、詳細は以下の通りです。
(ちなみに、CDは現在も販売中で買い物カゴに移動させられましたが、ビデオテープは完売とのことです…。)
創業14年で、売上400倍・2000億円。同業やマスコミからの強烈なバッシングの中、常に“お客様の都合”最優先の現場任せ経営が支持され、13期連続で増収増益中
こちら、どうやら2005年頃に開催された講演会の様子が記録されているようで、ということは今から20年近く前の出来事になりますね…。
それにしても、詳細を見て驚いてしまいました!「お客様の都合最優先」という一文から、20年近く経過しても安田氏の軸がまったくブレていないこと、皆さんお分かりでしょうか?
検証まとめ
 さて、ここまで安田隆夫氏の生まれから創業、成功に至るまでの経営哲学などを口コミを交えて紹介してきましたが、やはりコンセプトであるCV+D+Aが根幹にあり、おもしろいから店舗に行ってみようと消費者を動機づけしたことが一番の強みになっているようですね。
さて、ここまで安田隆夫氏の生まれから創業、成功に至るまでの経営哲学などを口コミを交えて紹介してきましたが、やはりコンセプトであるCV+D+Aが根幹にあり、おもしろいから店舗に行ってみようと消費者を動機づけしたことが一番の強みになっているようですね。
どんな企業も最初は小さな店舗で始まり、商売のノウハウを少しずつためて成功への道を進んでいくのですね。
泥棒市場というネーミングセンスや、本に記載されていた数々の語録は今後流通業界、小売業界に関係する人たちのみならず、多くの人に影響を与えるでしょうね。
今後注目していきたいのは海外への店舗進出とM&Aによる事業規模拡大です。より出店する地域の方々に楽しみを与えられる店舗にするには今の商品ラインアップや展示方法以外にも様々トライできる所はあるようがしてなりません。
ディスカウントストアの業界では世界ではウォルマートという圧倒的な大手企業が存在しておりますが、海外にてDONKIの名前が知れ渡るようになる日がいつか来るような気がします。
実際に、安田隆夫氏が取締役に復帰してからますます海外展開を進めています。これから店舗を訪れる方も創業した安田氏が何を大切にして創り上げた店舗なのかということに注目して、レイアウトや店内の仕掛けを楽しんでみてはいかがでしょうか。