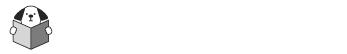※本記事執筆後の9月8日フジ住宅への賠償命令が確定しました。
東証プライム上場の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)で働く在日韓国人の50代女性が、民族差別的な文書を社内で配布され精神的苦痛を受けたとして、同社と同社会長に3,300万円の損害賠償などを求めた裁判(訴訟)。
一審、二審は原告側の勝訴が確定したものの、
同社側の違法性が認められない点も次々と浮き彫りになっています。
目次
フジ住宅裁判が裁判・訴訟された理由
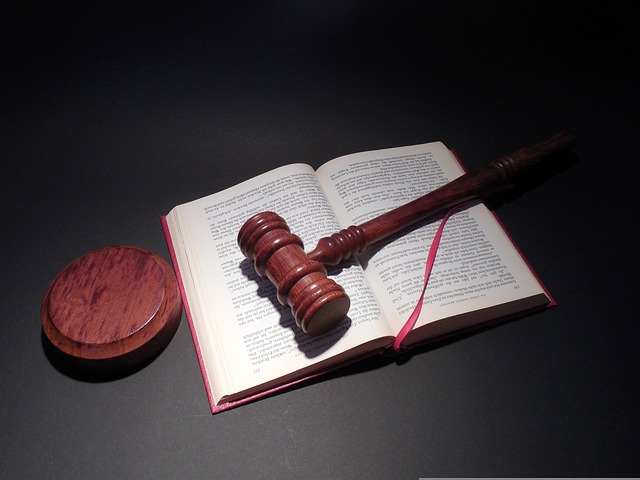
いわゆる「フジ住宅裁判」は2015年8月に提起され、2020年7月に大阪地裁堺支部、2021年11月には大阪高裁で判決が出ました。
いずれの裁判でも、同社側が何度も配布した文書の中には差別をあおるような内容が盛り込まれていたと認定。
高裁は一部資料の配布差し止めを命じ、配布を禁止する仮処分も下しました。
外国人を差別するヘイト文書を社内に配布?在日韓国人社員に訴訟される
高裁判決によると、同社側は2013年から在日韓国人らを侮辱する内容の文書を従業員に繰り返し配布。一審判決後も原告を批判する文書を大量に配ったとされています。
このため、一審で110万円だった慰謝料は、二審で132万円に増額されました。
しかし、同社側は「過度の言論萎縮を招くもので、到底承服できない」と最高裁に上告。
原告側と同社側の主張が真っ向から対立したまま、裁判は大詰めを迎えています。
原告個人への差別はなかったと認定
 一方、高裁判決は中国や韓国、あるいは北朝鮮などを批判するすべての文書の配布差し止めを命じたわけではありません。
一方、高裁判決は中国や韓国、あるいは北朝鮮などを批判するすべての文書の配布差し止めを命じたわけではありません。
同社会長が支持する教科書会社に関する従業員のアンケートの提出も強制されたものではなく、原告女性個人への差別はなかったとも認定しました。
事実、同社側の配布文書に含まれているのは、公の媒体の正当な論評と考えられる新聞や雑誌の記事、書籍です。
差別的な言辞が記されていたのは、同社側が従業員にYouTube動画を紹介した際、動画の画面と一緒に印刷された社外の第三者による書き込みなどに過ぎません。
原告側は人権侵害の証拠として、同社の従業員が役員に宛てた「日本人でよかったー、うれしい!と心から思いました」といった内容のメールを挙げました。

さらに、「大東亜戦争で日本は負けた。負けたというその結果から大東亜戦争の全てを正しくなかった、間違いだったと否定してしまうことはできないし、否定してはならないということだ」という書籍の一文を抜粋しただけのメールなども提出しています。
原告側は「日本人を称賛し又はその優越性を説くこと自体は差別的表現ではないとしても、(中略)過剰に流布されたりすれば、人種差別助長表現となる」と主張。
「歴史修正主義」に基づく記述も、同様の表現に当たるとしています。
もちろん、ヘイトを連想させる過激な言動が許されないのは当然です。
しかし、日本人としての誇りを説くだけでヘイトになるという論理には、首をかしげざるを得ない人も多いのではないでしょうか?
ちなみに、上記のメールには特定の他国民を貶めるような表現はもちろん、日本以外の国名も記されていません。
「ヘイトを行う企業」との原告側主張も不適切と認定

こうしたことから、高裁の判決理由にも「原告及びその支援団体が、(中略)同社が人種的憎悪・差別を正当化したり助長している、いわゆるヘイトスピーチ、ヘイトハラスメントを行う企業であると主張したり、喧伝したことは、適切な表現とは言い難いというべきである」と明記されています。
同社側も文書を配布した目的について、「私企業における従業員の教育・研さんのためであって、差別が目的ではなかった」と主張。
裁判でも「ヘイトハラスメントを行う企業ではない」という事実が認定されています。
原告女性に対しての配慮が足りなかった側面も
要するに、問題があったとすれば、「不適切な記述やコメントが、そのまま目に入る状態の文書を配布した」ということに尽きるでしょう。
文書を配布する前に民族差別的と受け取れる部分を隠したり、誤解を防ぐための注釈をつけたりしていれば、ヘイトハラスメントとして何ら問題視されなかったかもしれません。
同社はこの点に関し、一部不適切な表現を含むものがあったことを認めています。
そして、現在は社内資料に差別や中傷と受け取れるような表現が含まれることがないよう、十分に配慮しています。
フジ住宅とはどのような会社なのか

今回の訴訟・裁判により、フジ住宅に対してネガティブなイメージを抱いている方も少なからずいるかもしれません。
フジ住宅はどのような会社なのか、改めてみてみましょう。
フジ住宅の会社概要
| 商号 | フジ住宅株式会社 |
| 創業/設立 | 昭和48年1月22日/昭和48年1月22日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 宮脇宣綱 |
| 本社所在地 | 〒596-8588 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号 |
| 資本金 | 48億7,206万円 |
| 従業員数 | 922名(連結1,238名)*パート社員 |
| 証券コード | 8860 |
| 上場取引所 | 東証プライム市場 *2022年4月4日現在 |
| 事業内容 | 分譲住宅事業 住宅流通事業 土地有効活用事業 賃貸及び管理事業 建設関連事業 |
| 公式サイト | https://www.fuji-jutaku.co.jp/ |
フジ住宅は東証プライム上場企業であり、2023年3月期の売上高114億円、社員数は1,222名(連結)と、業界でも大手の老舗総合住宅メーカーです。
1974年の創業以来、約50年に渡り「売りっぱなし・建てっぱなしにしない」という企業理念のもと、手掛けた住宅になにかあれば、即時に駆けつけられるエリアに限定して事業を展開。顧客との信頼関係を非常に大切にしています。
また、人材育成にも注力しており、問題となった資料配布も社員教育の一環であったと考えられます。
社風や働きがいは?フジ住宅社員の口コミ評判

フジ住宅の内情を知るべく、元社員や現社員からの評判・口コミを調査しました。
ホワイト企業に選出されるのは当然の結果
風通しが良く、まじめな会社である。個人の立場を理解し、適材適所での配属をしてくれる。上司とのコミュニケーションもとりやすい。不平不満があれば、そのまま上司に伝える事が出来る。体調の事、家族の事を大切にしてくれる。社員を大切にしてくれる会社である。資格取得時には資格の種類に応じて、祝い金が支給される為モチベーションが上がる環境である。上司によって、働きやすさは変わる為、配属の部によっては働きにくい場合もあるが、ありのまま相談する事によって解決策を導いてくれる。社員の定着率も非常に高い為、ホワイト企業に選出されるのは当然の結果である。
引用元:https://www.openwork.jp/one_answer.php?vid=a0A2x00000KEG9E&qco=1
社員の幸せややりがいを大切にしてくれる会社
経営理念をとても大切にしている会社です。 最初はあまりにも経営理念といわれつづけることや、体育会系な雰囲気に戸惑うかもしれませんが、実際には社員の幸せややりがいを大切にしてくれる会社だと思います。 一般的な大手企業のような派閥のようなものもなく、部署間の隔たりもありません。会社全体で協力体制をしっかり整えているような感じで、部署間や部署内でも助け合いの精神がしっかりあるような感じでした。
引用元:https://www.openwork.jp/one_answer.php?vid=a0A1000002MCXyp&qco=1
人に喜ばれる仕事か好きな人にとっては大変やりがいがある
部署、担当業務にもよるであると思うが人に喜こばれる仕事か好きな人にとっては大変やりがいがあると思う。 経営理念上、感謝する心が成長に繋がるという面もあり仕事をする中で感謝の言葉を多く耳にする職場環境である。 自己成長したい気持ちがあれば、積極的かつ自発的に上司に相談することでスキルアップできる。 受け身であると、当然現状維持のままであり自ら成長したい気持ちを発信することが重要である。
引用元:https://www.openwork.jp/one_answer.php?vid=a0A1000002MBFyO&qco=4
このようにフジ住宅は社員を大切にしており、多くの社員がやりがいをもって業務に取り組んでいることがわかります。
「言論の自由」の認識が問われる最高裁判決

同社側が積極的な差別行為を図ったのではないという論理が成り立つことは、
「同社において、民族差別が行われており、本件活動への参加が強要されているかのような新聞報道がされたのは事実と異なるというべきである」という高裁の判決理由からも読み取れます。
多くのメディアは「報道が不適切」という判決理由はもちろん、配布の差し止め・禁止の対象になっていない文書が存在することも伝えていません。
このため、世間一般が裁判について誤った捉え方をしてしまっている可能性が否定できないのです。
これまでの判決に対しては「私企業の経営者の言論の自由をどう考えているのか?」という疑問の声も上がっている中、最高裁がどのような判決を下すのかが注目されます。
ブルーリボンに政治的主張があるという不可解
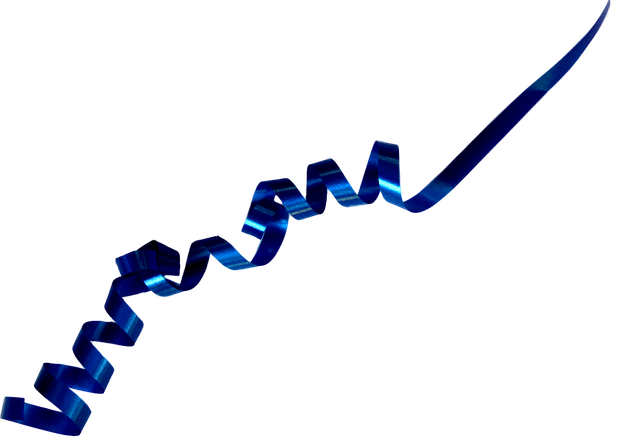
さて、「フジ住宅裁判」は法廷における原告側の行動がきっかけとなり、もう1つの訴訟を生み出しました。
いわゆる「ブルーリボン訴訟」です。
2017年12月、大阪地裁堺支部における「フジ住宅裁判」の第9回口頭弁論に詰め掛けたのは、「ヘイトハラスメントストップ」と書かれたバッジをつけた原告女性の支持者たちでした。
これに対し、同社側は2018年3月の第10回口頭弁論で「富士山と太陽」を描いたバッジをつけて入廷。
裁判所は「メッセージ性がある」として、双方のバッジを外すように指示しました。

法廷内の混乱を回避するため、裁判所が法律に基づく「法廷警察権」を行使したのは賢明だったかもしれません。
これにより、バッジをめぐる問題は一件落着したかに見えました。
しかし、「法廷警察権」の行使は、これにとどまりませんでした。
2018年5月の第11回口頭弁論で、同社会長が日頃から着用しているブルーリボンバッジにまで、裁判官から同様の指示が出されたのです。
言うまでもなく、ブルーリボンバッジは北朝鮮による拉致被害者の救出を願う国民運動のシンボルに他なりません。
そもそも在日韓国人である「フジ住宅裁判」の原告女性に対し、ブルーリボンバッジを「メッセージ性がある」と決めつけるのは無理筋だと感じる人も少なくないでしょう。
「北朝鮮人権法の趣旨に反する」との声も

北朝鮮人権侵害対処法は国が拉致問題解決に最大限努力すると定め、政府の拉致問題対策本部も「ブルーリボン運動」について国民の参加を求めています。
歴代の首相をはじめとする主要閣僚もブルーリボンバッジを常に着用していますが、「フジ住宅裁判」でのバッジ着用は一審判決までどころか、控訴審でも禁じられました。
2020年11月、同社会長と支援者の計3人は「法廷内でブルーリボンバッジの着用を禁止し、バッジを外すように指示されたことは、表現の自由を認めた憲法に違反する」として、計390万円の国家賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。
同社会長は「ブルーリボンバッジに政治的な意図などない」と主張しています。
国側は請求棄却を求めて争う姿勢ですが、以下の2点を疑問視する世論が強まっているのは事実です。
メッセージが込められた社員章やロゴマークなどは法廷内で禁止されていないのに、なぜブルーリボンバッジは認められないのか?
国が拉致問題解決に最大限努力すると定めた北朝鮮人権侵害対処法の趣旨との整合性を、国の機関である裁判所はどう取るのか?
正しい審理を進める上で、同社会長らはブルーリボンバッジ着用を禁止した堺支部裁判官(当時)の証人尋問も求めています。
国側は「必要ない」との立場を崩していません。
しかし、政府は2021年3月の衆院内閣委員会で「ブルーリボンは拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボル」と明確に答弁しているのです。
「言論と表現の自由」は国民の重要な権利に関わる問題
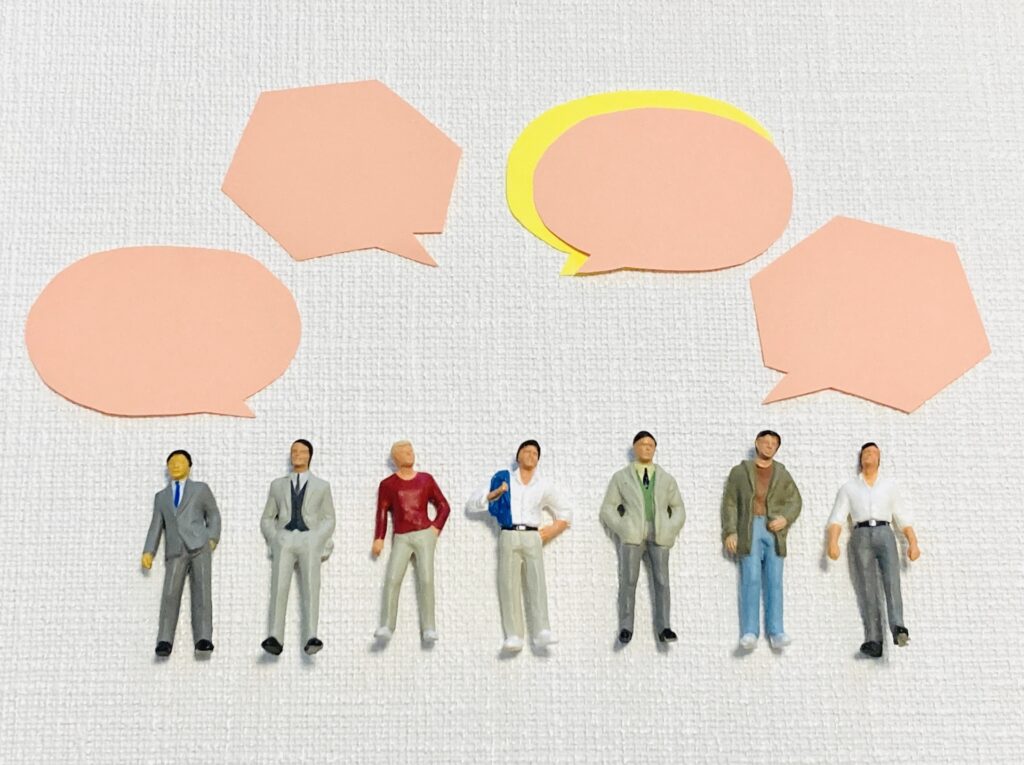
政府が「国民運動のシンボル」と認めているバッジの着用を国家権力が禁止するというのは、明らかに矛盾しているようにも映ります。
日本国内、しかも国の機関の中に、ブルーリボンバッジを着用したくてもできない場所が存在している状況は、何も間違っていないと本当に言い切れるのでしょうか?
「フジ住宅裁判」で争われている「言論の自由」と同様、憲法で手厚く保障された「表現の自由」をめぐる「ブルーリボン訴訟」は、国民の重要な権利に関わる問題であるとも言えるでしょう。